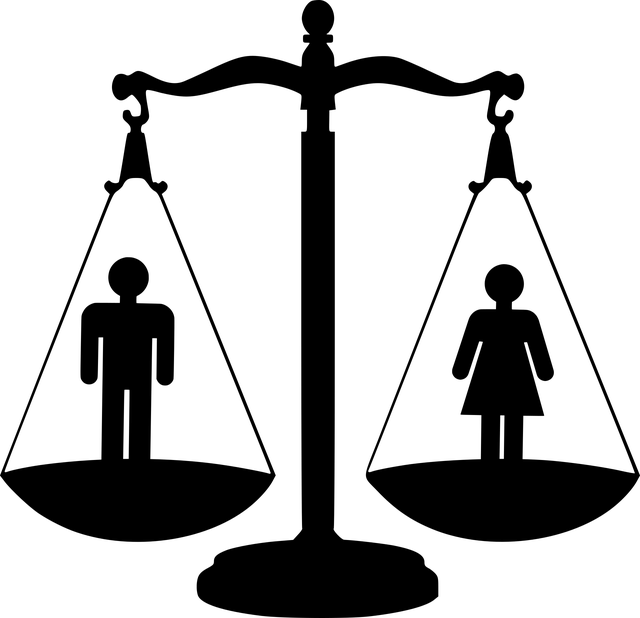
経営者の方はご存知かもしれませんが、2020年4月から同一労働同一賃金が施工されます。
現在2019年10月末日なので、実質すでに半年を切っています。
同一労働同一賃金という名前からしてどのような制度なのかはある程度予想はつくと思いますが、それでもあまり詳しくないという方が未だにいるかも知れません。
経営者になったばかりの人や同一労働同一賃金についてあまり詳しくない方のために、同一労働同一賃金という制度がどんなものかお話します。
同一労働同一賃金について
同一労働同一賃金とは、働き方改革のための制度の一つです。
わかりやすくいえば、年令や性別、国籍、そして雇用形態といったもので賃金の格差が生まれないように、同じ内容の労働の場合はすべて同じ待遇と賃金を提供するという内容です。
現在、日本では収入格差が問題になっています。
中でも正規雇用と非正規雇用の格差は非常に大きく、収入面だけではなく待遇に関しても大きな違いが生まれています。
一例では、正規雇用者は社員食堂は使えるが、非正規雇用者は使用が禁止されているといった事例も過去に確認されています。
そういった格差をなくすための施策が働き方改革であり、
同一労働同一賃金はその改革のための一つの手段です。
あくまでも「不合理な場合」のみ
なお、同一労働同一賃金は必ずしも統一しなければならないというわけではないことにもご注意ください。
同一労働同一賃金は、不合理な待遇にのみ適用されるものであり、適正な場合は給料の統一をしなくても問題ないのです。
例えば、上でも紹介したように正規雇用者は食堂を使えるのに非正規労働者は使ってはいけないというのは明らかな不合理です。
そのため、この場合同一労働同一賃金の施策により、非正規雇用者も同等も待遇が受けられます。
しかし、工事現場で働く人が「危険手当」を貰えるのに対し、オフィスで働く事務の人には危険手当が支払われないというのは不合理ではありません。
危険が発生する現場で作業しているのと現場ではないオフィスで働いているのですから、この場合は適切だといえます。
また、正規雇用者の業務に非正規雇用者の勤怠管理や作業指示といった非正規雇用者ではできない重要な責任を背負っている場合も同様に、不合理には当てはまらないと言えるでしょう。
詳しくはガイドラインを
上で紹介したように、同一労働同一賃金は不合理な場合にのみ適用されるものであり、そうでない場合には今までと同じような待遇で問題ありません。
つまり、きちんと正当なお給料を支払っていれば、同一労働同一賃金において大きな変化を行う必要性はないということです。
しかし、自分では正しいと思っていても、世間一般では間違っているという解釈がされていることもあります。
そのため、経営者の方は一度同一労働同一賃金のガイドラインを熟読することをおすすめします。
厚生労働省では同一労働同一賃金に関するガイドラインを制作しており、正当化不合理科の線引をわかりやすく紹介してくれています。
基本給や賞与、福利厚生などの各種手当ついて説明しているので、もし気になることがあるのでしたら同一労働同一賃金のガイドラインをチェックしましょう。
劇的に変わることはない
2020年4月から始まる働き方改革ですが、基本的にまっとうな経営をしているのであれば劇的な変化はほぼないといって良いでしょう。
きちんと正しいお給料を支払い、正しい待遇で雇っていれば、行政指導が来る確率は皆無と言って良いです。
しかし、それでも絶対に問題ないとは断言できません。
見えないところで何かが問題になっているという可能性も十分あるのです。
今一度、会社の待遇面を見直してみてはいかがでしょうか。